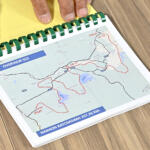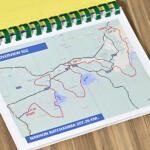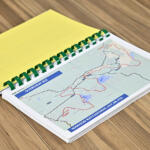クルマを育て・人を育てるためにモータースポーツは重要!
三菱自動車は第46回バンコク国際モーターショーにおいて、2025年8月8日から開催されるアジアンクロスカントリーラリー(以下AXCR)に参戦するために新しいカラーリングをまとった「トライトン」のT1仕様(改造クロスカントリー車両)を披露した。これまで6日間、約2000kmで競われてきたAXCRだが、じつは今年は第30回となる記念大会だ。のべ8日間・約2500kmという「拡大フォーマット」で争われ、タイ東部のリゾート地パタヤをスタートし、タイ国内の山岳・密林地帯を周ってカンボジアへ入り、ゴールとなる首都プノンペンを目指す。
 バンコク国際モーターショーに展示されたAXCR2025仕様のトライトンの真横画像画像はこちら
バンコク国際モーターショーに展示されたAXCR2025仕様のトライトンの真横画像画像はこちら
トヨタやいすゞ、フォードなど、より大排気量のライバル車に対して三菱トライトンは2.4リッターディーゼルターボで戦う。トライトンでの初挑戦となった2022年はいきなり総合優勝、2023年は3位、そして2024年はラリーの折り返しで首位を奪取するも、エンジントラブルにより無念のリタイヤとなった。今年はエンジンの耐久性を強化した上で、足まわり、その他の細部まで細かく熟成させた仕様とし、捲土重来を図る。
 2022年にAXCRで総合優勝した三菱ラリーアートチーム画像はこちら
2022年にAXCRで総合優勝した三菱ラリーアートチーム画像はこちら
いわばバンコク国際モーターショーで2025年の参戦車両を発表した事実に、三菱の並々ならぬモチベーションを見い出せる訳だが、チーム三菱ラリーアート総監督の増岡 浩さんに、今年の体制からAXCRへの心境を語ってもらった。
──まず三菱ラリーアートとしてのAXCRへの取組みを教えていただけますか。トライトンで参戦したのが2022年なので今年が4シーズン目ですね。
増岡 浩(以下増岡) : そうです。それ以前にもアウトランダーPHEVが出たばかりのころだから、もう10年以上前ですが、2013年から会社として参戦していました。ツインモーターの4駆のPHEVでも、しっかり走れるところを証明しようじゃないかと。世間で電動車のバッテリーに対して不安が囁かれていましたから、底を打ったり、水に浸かったりしても問題ないクルマだということを示したかったんです。
──トライトンからではないんですね。
増岡:それ以前にも先々代トライトンなどで、車椅子のドライバーさんや元GPライダーの青木琢磨さんがプライベーターとしてハンディドライブ仕様で走るのをラリーアートがサポートしたことがありました。そんな歴史があります。
 三菱ラリーアートチームの増岡 浩総監督画像はこちら
三菱ラリーアートチームの増岡 浩総監督画像はこちら
──ではラリーレイド的な参戦はパリ・ダカール以来とはいえ、アジアでも長く続けられているんですね。
増岡:AXCRはパリ・ダカールラリーと比べて日数や総合距離が比較的コンパクトで、ある意味、参戦しやすい。運営というか主催しているのは日本のオーガナイザーで、もともと8月の夏季休暇を利用してアマチュアのラリーストにも広く門戸を開こうと。なので日本のプライベーターも結構走っています。でもFIA格式でプロフェッショナルチームと同じ土俵で走るという、本格的でいて身近、そこが魅力的なラリーですね。クロスカントリーを謳うからには2カ国以上、ラオスやマレーシア、そして今年のようにカンボジアをまわったりします。
──三菱自動車、ラリーアートとしてトライトンでAXCRに参加する意義とは?
増岡:三菱自動車としてはモータースポーツ活動をしばらく休止していたのですが、やはりラリーアートとして活動したい。それにアジアがメイン市場となるトライトンがあるのでPRも兼ねられます。三菱は世界中に販売拠点があるわけですが、トライトンは100カ国以上に出荷しているなかで、それこそタイ、マレーシア、インドネシアは屋台骨となる重要市場なんです。そこでAXCRを通じて、それだけ東南アジア市場を重視しているというメッセージ、情報発信できればというのがあるんです。
 AXCRについて説明する増岡 浩総監督画像はこちら
AXCRについて説明する増岡 浩総監督画像はこちら
──AXCR参戦を通じて、三菱自動車社内の人材を育成する側面もあるんですか?
増岡:はい。外だけでなく社内イベントも積極的に行ってアピールしています。やはり長いことモータースポーツを離れていたので、社員のモチベーションを上げる点ではもちろん、クルマづくりでもさまざまな部署から色々なスペシャリストを集めていますよ。市販車ベースとはいえ、電子制御とか統合制御は実際に触っている人じゃないと歯が立ちませんから。社内でもいいチーム作りができていますし、先日も岡崎にタイ現地のチーム代表と、エースドライバーのチャヤポン・ヨーターを迎えて、トークショーをやったり、じゃんけん大会で勝った者に助手席体験をさせたり。社内向けのイベントでしたけど盛り上がりましたね。
──やはりモータースポーツ好き、やりたい人たちがけっこう社内にいた、ということですか?
増岡:はい、そういった人たちが三菱自動車に入社することを選んでくれているので、やはり機会を作って携わってほしいですよね。私としては、テストドライバーはもちろん、設計者やデザイナーにもなるべくクルマに乗らせるようにしています。たとえばですけど、自分がすごく設計でこだわったところが、じつは走りには影響ないとか、あるとか、こうしたら使いやすくなるとか。そうした気づきが担当者の意識を変えますから。クルマを育てる、人を育てるという意味で、モータースポーツは重要だと思いますね。モチベーションにも繋がりますし。