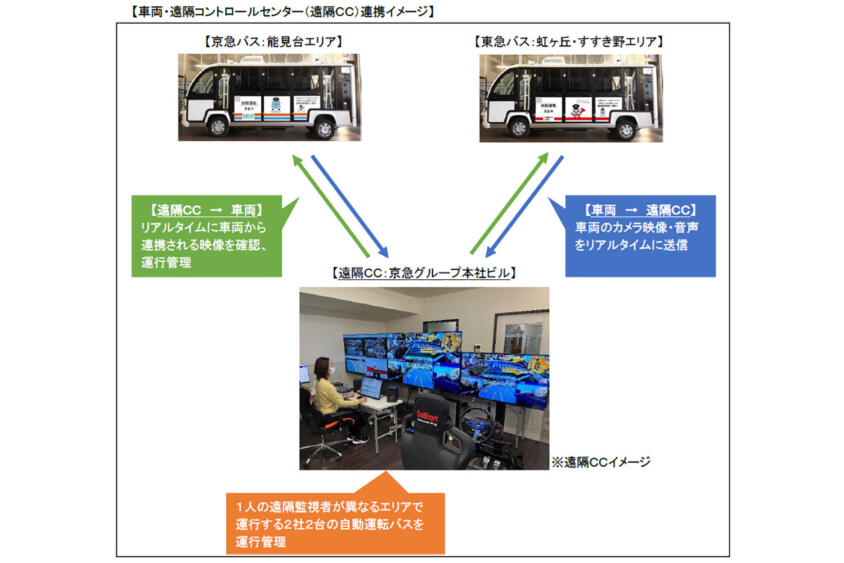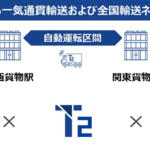この記事をまとめると
■日本通運、全国通運、日本フレートライナー、JR貨物、T2が実証実験の検討を開始
■自動運転トラックと貨物鉄道を組み合わせたモーダルコンビネーション実証実験だ
■目的は環境問題や人手不足など、物流業界が抱える問題の解決
各輸送モードの特性を生かして問題を解決
自動運転システムの開発などを手がけるT2と日本通運、全国通運、日本フレートライナー、JR貨物の5社が、自動運転トラックと貨物鉄道を組み合わせた、モーダルコンビネーション実証実験の検討を開始した。これは、トラック、自動運転トラック、鉄道を組み合わせて、環境問題や「2024年問題」による人手不足など、物流業界が抱える課題解決に向けた取り組みを行おうというものである。
近年、モーダルシフトという言葉をよく聞くが、これは環境負荷の高いディーゼルエンジンを使用する大型トラックから、環境負荷が比較的低いとされる鉄道、船舶に、コンテナ輸送の輸送モードを変更しようという考え方だ。あくまで、環境の観点から検討されている方法である。これに対してモーダルコンビネーションは、トラック、鉄道、船舶など各輸送モードの特性を生かしながら組み合わせ、よりメリットのある輸送を実現しようというものだ。
 実証実験のイメージ画像はこちら
実証実験のイメージ画像はこちら
JR貨物は以前から、モーダルコンビネーションを検討していた。その具体的な推進施策として、以下のようなことが推進されている。
・レールゲート(貨物駅内物流施設)に加えて、駅ナカ、駅チカのコンテナ積み替えステーションを拡充し、緊締車(コンテナ専用車)だけではなく、一般トラックでも駅に荷物のもち込みや引き渡しができるようにする
・パレットデポ(パレットのサービス拠点)の併設や、梱包用の養生材貸し出しサービスなどを組み合わせて、物流作業の利便性向上を図る
・物流Maas(データの連携と自動化で、物流を最適化する取り組み)を推進し、トラック求貨求車システムと組み合わせて、ワンストップで予約をできるようにする
・中距離帯におけるネットワークの強化を図る
・フィジカルインターネットに対応し、パレット単位での引き受けも視野に入れる
・大型コンテナ荷役システムを検討する
・スワップボディ車との連携を検討する
・大型コンテナに対応した次世代低床貨車を開発する
今回検討される実証実験では、たとえば九州・四国・中国地区から東北・北海道地区に荷物を送ると想定した場合、まず出荷先から九州・四国・中国地区の貨物駅に普通トラックで荷物を運び込む。そこから、関西の貨物駅までは鉄道が輸送。関西・関東間を、自動運転トラックが運ぶ。関東の貨物駅から、東北・北海道地区の貨物駅までは再び鉄道で輸送し、そこから荷受け先までは普通トラックが配達するというイメージだ。
 実証実験のイメージ画像はこちら
実証実験のイメージ画像はこちら
関西・関東間が自動運転の対象となっているのは、新名神・新東名高速道路が自動運転に向けて、インフラ整備をする予定になっているからだ。また、2025年3月をめどにスワップボディトラックと、貨物列車の両方に積載可能な31フィートタイプの共用コンテナも開発されることになっている。このコンテナは、貨物列車からスワップボディトラックに直接載せ替えることができ、貨物の積み替えに要する作業時間を大幅に短縮することができるのだ。
CO2削減などの地球環境改善・ドライバーや運転士不足・労働環境の改善など、物流業界は喫緊の課題を数多く抱えている。これらを解決してスムースな物流体制を構築するためには、モーダルコンビネーションのような取り組みが不可欠である。5社の実証実験が実現し、課題解決の道筋ができることを多くの物流関係者が期待しているのである。