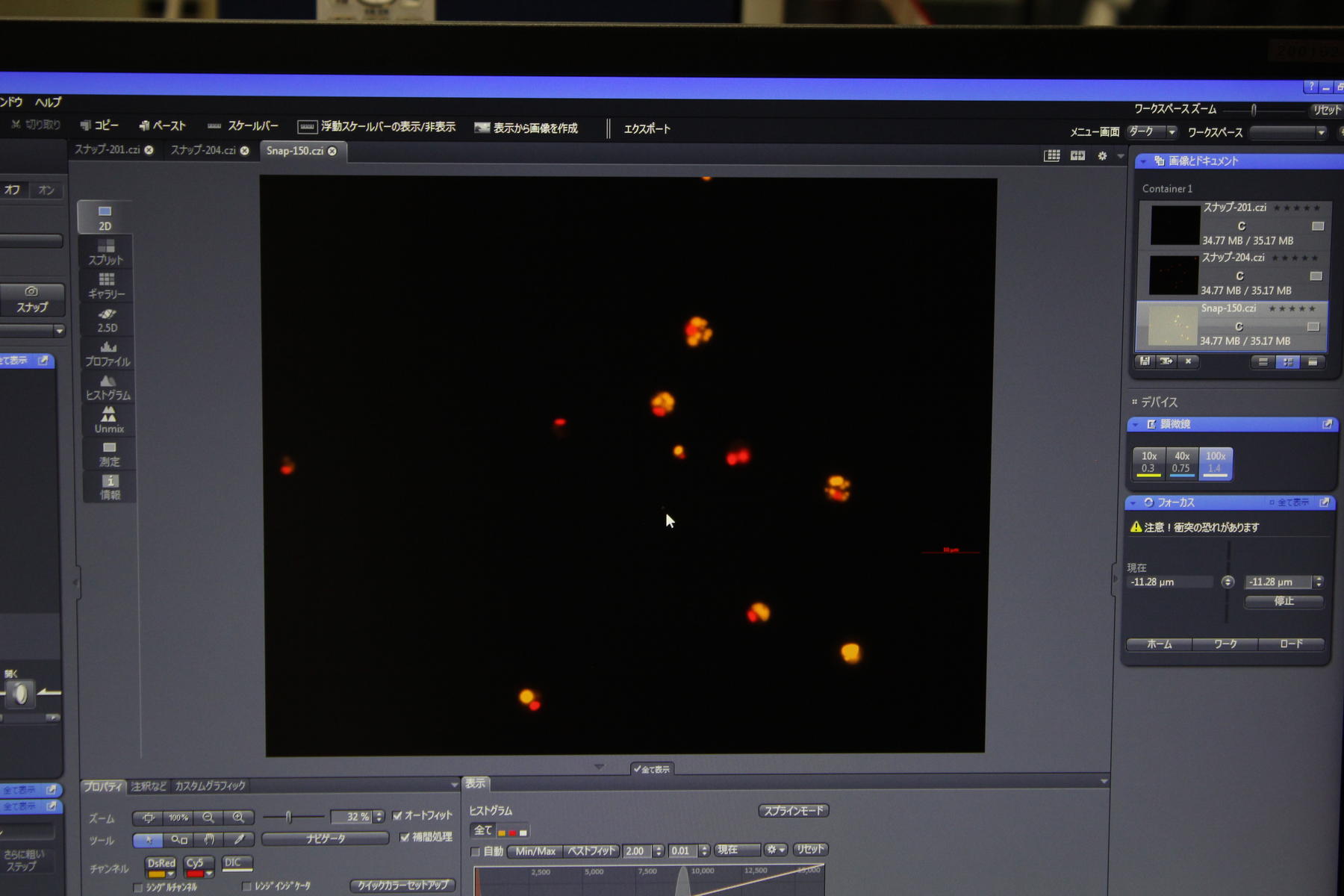この記事をまとめると
■バイオ燃料の開発が進められている
■植物などから作り出される燃料をバイオ燃料という
■食品になる植物を使うと食料問題を招き本末転倒になるなど問題は多い
第2世代のバイオ燃料も誕生
カーボンニュートラルを達成する手段として、クルマではEVやFCEVが筆頭に挙げられるが、製造時から廃棄処分(リサイクル)まで考えると、それらのクルマとて完全なカーボンニュートラルは難しい。むしろエンジン車のほうが製造時やリサイクル時の環境負荷は小さいから、あとは使用時の二酸化炭素発生を抑えることができれば、カーボンニュートラルへと近づける。そんな考えのもと、合成燃料やバイオ燃料が開発され、使われ始めている。
合成燃料は二酸化炭素から酸素を取り出し、不安定な一酸化炭素にした上で水素と結びつけることで炭化水素、すなわち燃料を作り出す技術だ。材料は二酸化炭素と水素、そして電力があればできるが、これも二酸化炭素を発生させずに作り出すのは難しい。燃料を作り出すには、それ以上のエネルギーを投じないとできないのは、物理の法則で決まってしまうからだ。バイオ燃料はそんな物理法則の上にも成り立つ、現在もっとも合理的なカーボンニュートラル燃料だ。
 バイオ燃料のイメージ画像はこちら
バイオ燃料のイメージ画像はこちら
そんなバイオ燃料にもさまざまな種類がある。その歴史は古く、ブラジルでは石油の代わりにサトウキビから作られるアルコールを燃料として利用してきた。トウモロコシからもアルコールは作られ、欧米でも利用されてきた。しかし、食糧にもなる原料を燃料へと転換することは食糧との競合になり、食糧価格の上昇へとつながるリスクがある。そんなことで、この第1世代のバイオ燃料は利用できる環境が限られるのだった。
そこで生まれたのが第2世代のバイオ燃料だ。これは成長の早い植物を原料として、やはり発酵させてアルコールを作り出す。しかし、糖分の少ない植物の食物繊維からアルコールを作り出すのは、やや効率が悪く時間もかかる。
ちなみにアルコールを作り出せれば、そこからメタネーション(メタン化処理)することで天然ガスと同じものが作れ、さらに合成してディーゼル燃料を作り上げることもできる。ガソリンと比べ、自己着火する油であれば幅広い燃料に対応できるディーゼルならではの強みが活かせるのだ。
糖質ではなく、油(炭化水素)を直接作ってもらう方法もある。それは藻の仲間に体内に油を溜め込む種がいて、それを培養することで油を作り出し、燃料の原料とするのだ。この微細藻類による油からの生成が第3世代のバイオ燃料である。これまでもさまざまな機関がこの研究を行っているが、いまだ大量生産にはたどり着いていない。
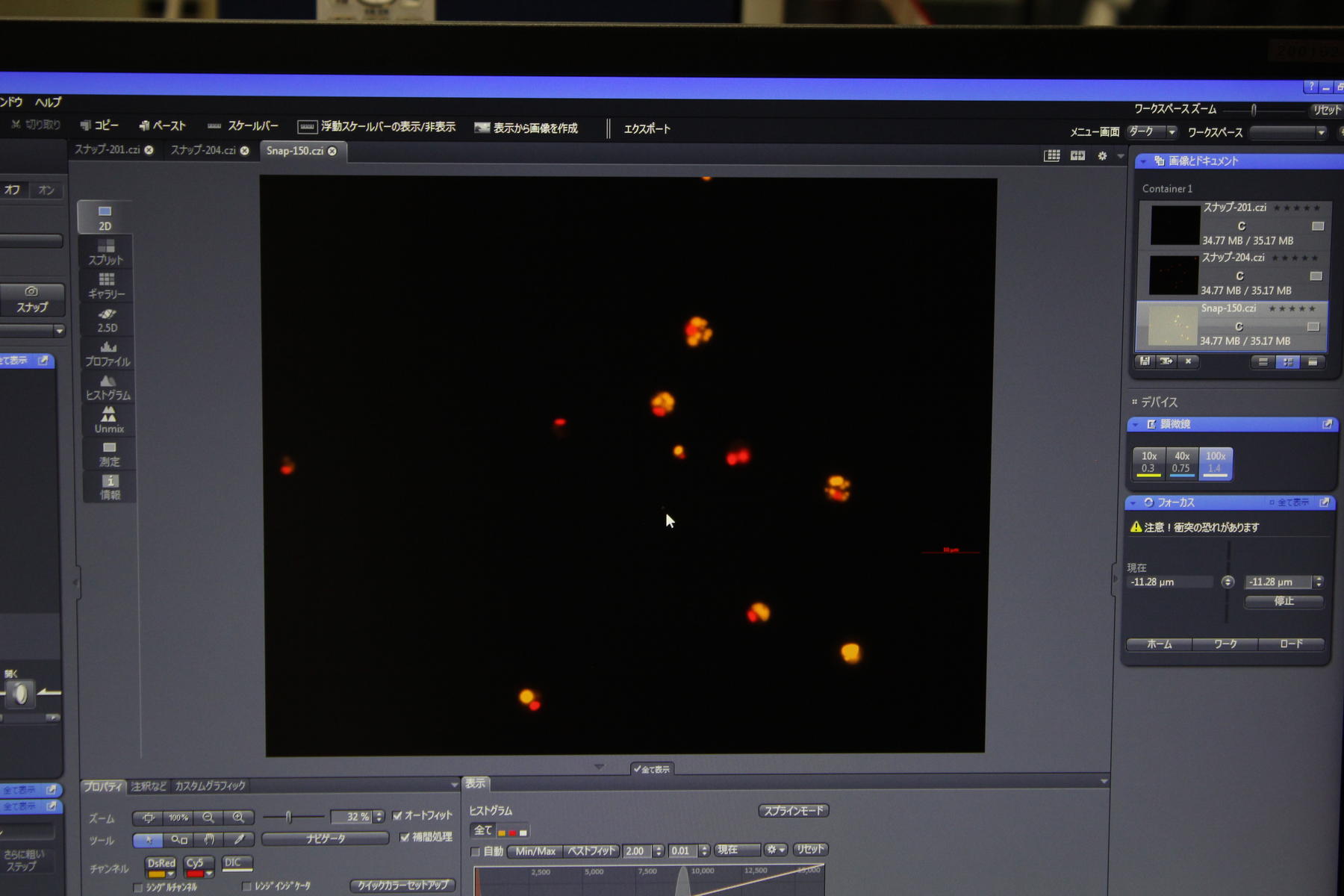 バイオ燃料のイメージ画像はこちら
バイオ燃料のイメージ画像はこちら
一方、ディーゼルや航空機用燃料として、現在急速に普及しているがHVO(水素化植物油)やSAF(持続可能航空燃料)といったものは、食廃油を回収して改質しているもので、とてもじゃないが航空業界や運輸業界を支えるほど原料があるわけではない。それどころか飼料として利用してきたぶんまで、燃料にまわされており、価格も高騰している。
本当の意味でのバイオ燃料が普及しなければ、エンジン車の明るい未来はやってきそうにない。