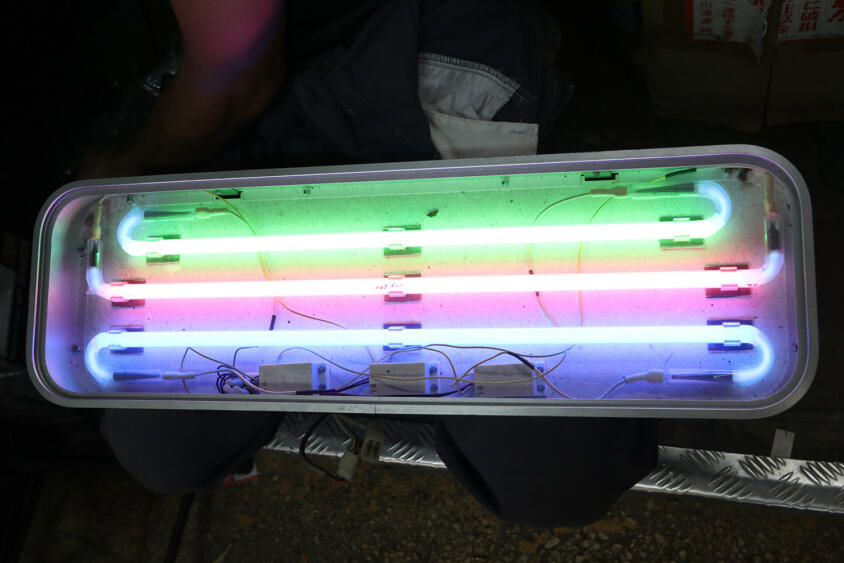この記事をまとめると
■タクシーには「営業区域」というのが定められており好き勝手お客を乗せられない
■「営業区域」はその地域におけるタクシーの需要と供給によって成り立っている
■ライドシェア解禁の前に営業区域の見直しも必要という声も少なくない
タクシーを縛り付ける「営業区域」とは
タクシーやライドシェアなど旅客輸送には、営業区域が定められています。定められている営業区域を無視して区域外で乗客を乗車させたり降車させたりすることは法律で禁止されているため、旅客輸送をするドライバーは気をつけなければなりません。
 タクシー乗り場のイメージ画像はこちら
タクシー乗り場のイメージ画像はこちら
しかし、営業区域について調べてみると、「なぜ、この場所が営業区域に入っているの?」と思ってしまう区域があります。今回は、タクシーやライドシェアの営業区域の謎について解説します。
許可が必要なタクシーなどの営業区域
タクシーやライドシェアなど乗客を乗せる旅客輸送は営業区域が定められています。この営業区域は、地域の実情をはじめ、さまざまな事情や状況を勘案し、地方運輸局が指定しているため、タクシー会社が自由に決められるものではありません。そのため、タクシー会社は、法律に基づき、営業区域ごとに許可を得て事業をしています。
「なぜここも営業区域内なの?」という場所について
タクシーやライドシェアなどに影響する旅客輸送の営業区域ついて調べてみると、おおよそ地域ごと(市区町村ごと)にまとまっている傾向が見られます。しかし、東京都の営業区域を見てみると、東京特別区(武三交通圏)が「23区」「武蔵野市」「三鷹市」となっています。このような営業区域となっている理由はなんなのでしょうか。
そもそも営業区域は、地域の事情やタクシーの需要・供給のバランスなどによって決められます。そのため、営業区域によって範囲が広かったり狭かったりするだけでなく、一部の地域(市区町村)が入っているというケースがあるのです。
 西国分寺駅とタクシー画像はこちら
西国分寺駅とタクシー画像はこちら
東京特別区(武三交通圏)も、需要と供給のバランスの兼ね合いによって、「23区」に加え「武蔵野市」「三鷹市」が含まれていると考えられます。また、23区からベッドタウンである武蔵野市や三鷹市に帰る人が多く、23区の営業区域に武蔵野市・三鷹市が入っていると、タクシーにとっても乗客にとっても都合がいいということも理由のひとつといえるでしょう。
このように、タクシーの需要と供給やタクシー利用者と事業者のメリットなどを総合的に勘案して、東京特別区(武三交通圏)も含めた営業区域が定められています。