片道で稼いでも帰りは奇跡でも起きない限り同じ距離を「回送」
あるタクシー料金のシミュレーション検索ができるサイトで、東京駅から名古屋駅まで、深夜に高速道路走行を優先にして計算したら、14万1850円という金額が出た。「これなら乗務員もホクホクなのでは?」と考えがちだが、もちろん乗務員個々で反応は異なるが、手放しで嬉しいというわけでもないようだ。単純にタクシー料金が14万円というのはすごいが、お客を送り届けたあとは、たまたま送り先から東京までタクシーで移動したいという、まさに奇跡的なお客が現れない限り、回送で東京まで帰ってくることになる。
 タクシー画像はこちら
タクシー画像はこちら
いまどきはアプリ配車に積極的なタクシー会社の乗務員ならば、原則営業区域内の通常営業でもかなり稼ぎが良く、年収1000万円も珍しくない。乗り逃げだけでなく、乗務員の平均年齢の高さを考えても、超長距離の営業はハイリスクがより目立ってしまっているのが現状だ。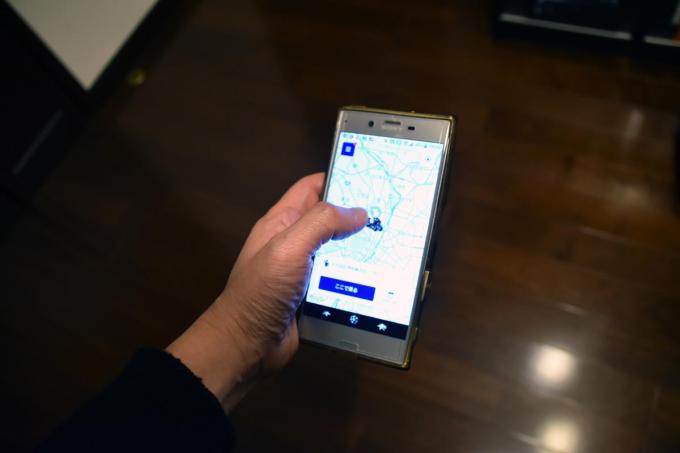 タクシー画像はこちら
タクシー画像はこちら
筆者はよく自宅(埼玉県)までタクシーを呼んで利用するのだが、早朝などは前述したように勤務時間や走行距離の関係もあるので、必ず目的地がどこかを聞かれる。そして配車されたタクシーに乗ると、「この時間で東京といわれると私はもう行けないのでよかった」と乗務員さんが話してくれた。 タクシー画像はこちら
タクシー画像はこちら
大けがをして電車に乗るのが難しい時に、仕事で往復タクシーを利用して自宅から東京まで移動していた時がある。その時も昼間から都心までの客だからさぞ嬉しいのかなあと思ったら、「参ったなあ昼から用事があるんだよね」と意外な返事が返ってきた。
とくに朝に都心から東京隣接県までの利用などは、帰りの通勤ラッシュに巻き込まれるので、それを嫌がる乗務員も多いと聞く。
世界的には、営業区域内で回数を多くお客を乗せたほうが儲かるという考え方が主流となっているようだ。インドネシアでジャカルタ隣接市からジャカルタまでタクシーに乗ったら、最初のタクシーが高速道路のインターチェンジ手前で停車した。すると乗務員はタクシーを降り、仲間と話をしたあと、その仲間のタクシーに乗り換えるように言ってきた。すると仲間は乗せてきた乗務員に、おそらく乗車地からインターチェンジまでの料金を支払ったようだ。そして仲間のタクシーで無事ジャカルタに到着した。 タクシー画像はこちら
タクシー画像はこちら
これこそまさに、最初のタクシーは長距離を嫌がり、そして途中で請け負った乗務員は長距離メインで営業しているということの顕著な例といえよう。
日本ではこのようなことはないが、乗務員のなかには近場でコツコツ稼ぎたいというひとや、“一発ロング狙い”をメインに営業している乗務員さんなど、その営業スタイルは千差万別なのである。

