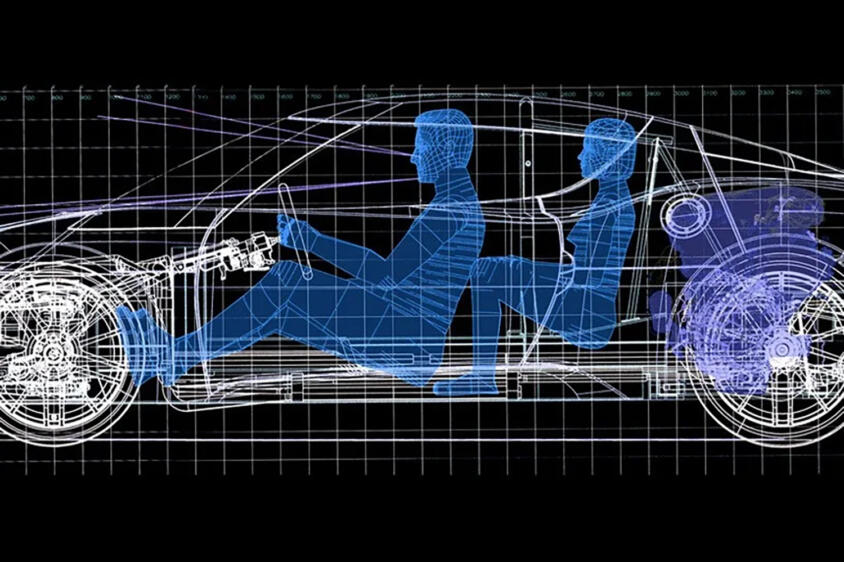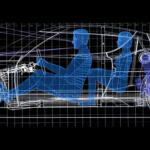そもそも貴重な個体で素性がハッキリしている
9月9日と10日にフェラーリの聖地であるイタリアのマラネロで開催されたフェラーリの70周年記念イベントに、1台のボロボロに見える365GTB/4、通称デイトナが姿を現した。
ボディのペイントは呆気にとられるほどカサカサ、前期型の証明であるプレクシグラスのヘッドランプ・カバーにはクラックが入り、新車時代には光を誇らしげに跳ね返していたはずのクロームのパーツ類には光沢のひとつもない。エンジン・ルームにも室内にも、埃が分厚く積もっている。まったく興味のない人が見たら、スポーツカーのカタチをした粗大ゴミのように思えるかも知れない状態だ。
 デイトナ画像はこちら
デイトナ画像はこちら
だが、このデイトナはイベント内で行われたRMサザビースのオークションで、140万〜170万ユーロ(イベント開催時の換算でおよそ1億8300〜2億2200万円)というエスティメート(この場合にはオークション会社のスペシャリストによる査定価格、あるいは予想落札価格)を超えた180万ユーロ(同じくおよそ2億3500万円)で落札され、世界中でニュースになった。これまたまったく興味のない人からすれば、どういうこと? と鳩が豆鉄砲を喰らったような気分だろう。
その一方で、ヒストリックカーの世界をよく知る人達にとっては不思議でも何でもない出来事であり、どこからも異論らしい異論は出てこなかった。それはいったいなぜなのか──? デイトナ画像はこちら
デイトナ画像はこちら
ヒストリックカーの世界に、「納屋モノ」という言葉がある。海外でもバーン・ファウンド(Barn Found)、つまり「納屋で見つかったモノ」と、まったく同じ意味合いの言葉が使われている。勘のいい人は想像がついたことだろうが、つまりは何らかの理由で納屋などに仕舞い込まれ、長い年月を経て発掘され、再び日の目を見たクルマのことを示す言葉である。 デイトナ画像はこちら
デイトナ画像はこちら
納屋モノは放置されていた期間が長く、可動状態にないのがほとんどだが、一方で実際に使用されていた期間が短く、走行距離も少なく、また生産されたときのオリジナリティをよく保っているケースが多い。見た目はボロボロであっても、そういう意味で価値は決して小さくなく、それがもともと貴重な車種であった場合には高額で取引されることも珍しくない。 デイトナ画像はこちら
デイトナ画像はこちら
もちろんレストレーションが施されて新車のように蘇らせられる場合もあるだろう。あるいは近頃の欧米でブームになりつつある、外観は発見されたときの状態をそのまま保ち、機関だけはしっかり手を入れて走れるようにする、プリザーヴド・カー(Preserved Car)と呼ばれる究極的にオリジナリティを追求したクルマへと仕上げられるかも知れない。
いずれにしてもそれらの素材とするのに納屋モノほど適したものはなく、新たなオーナーにとっては何よりのお宝となるわけだ。
今回のデイトナも、納屋モノの1台である。日本の岐阜県某所の納屋で眠りにつき、およそ40年ぶりに姿を現した。ステアリングが日本に上陸してからのいずれかのオーナーの好みのものに交換され、フロントグリル内に補助灯が追加され、ダッシュボードの助手席側に吊り下げ式のクーラーが備え付けられてる以外、ほぼ完全にオリジナル状態での発見だった。 デイトナ画像はこちら
デイトナ画像はこちら
もちろんそれだけでも充分な価値を持っているわけだが、単にそれだけだったら、さすがに今回ほどの落札価格とはならなかったことだろう。じつはこのデイトナ、ある意味では世界に1台といえる仕様で世に送り出されている貴重な個体だったのだ。
というのも、デイトナは、ドアやエンジンフード、トランクリッドこそアルミ製ながらボディ本体はスチール製が標準なのだが、この“12653”というシャシーナンバーを持つ個体は、セルジオ・スカリエッティの工場で最初から総アロイ製ボディを持たされて製造されているのだ。 デイトナ画像はこちらその当時はほかにも4台ほどのアロイ・ボディを持つデイトナが作られたといわれるが、それらはすべてグループ4カテゴリーを戦うためのレーシングカー。どんないきさつ──おそらくスペシャル・オーダーだと思われる──があったかはわからないが、ロードカーとして作られ、レザー張りのインテリアとアロイ・ボディが組み合わせられたデイトナは、これ1台しか存在しないのである。貴重な個体どころの騒ぎではない。そういう仕様のデイトナが日本のどこかにあるということは以前から関係者やマニアの間で語り継がれてきていたが、それがようやく姿を現した、というわけだ。
デイトナ画像はこちらその当時はほかにも4台ほどのアロイ・ボディを持つデイトナが作られたといわれるが、それらはすべてグループ4カテゴリーを戦うためのレーシングカー。どんないきさつ──おそらくスペシャル・オーダーだと思われる──があったかはわからないが、ロードカーとして作られ、レザー張りのインテリアとアロイ・ボディが組み合わせられたデイトナは、これ1台しか存在しないのである。貴重な個体どころの騒ぎではない。そういう仕様のデイトナが日本のどこかにあるということは以前から関係者やマニアの間で語り継がれてきていたが、それがようやく姿を現した、というわけだ。 デイトナ画像はこちら
デイトナ画像はこちら
この幻のような存在だった世界にただ1台のデイトナは、フェラーリの公式イベントで行われるオークションに出品されたことからも察せられるように、フェラーリ本社でクラシック・モデルのレストレーションや鑑定などを専門的に行う部門「フェラーリ・クラシケ」によって、ボディ、シャシー、パワートレインなどの製造番号がマッチしていることを確認されている。 デイトナ画像はこちらつまり”本物”であることにお墨付きがつけられているわけだ。また36390kmという数値のまま停まっているオドメーターの走行距離も、正確なものと判定されている。
デイトナ画像はこちらつまり”本物”であることにお墨付きがつけられているわけだ。また36390kmという数値のまま停まっているオドメーターの走行距離も、正確なものと判定されている。
さらには1969年9月にクルマが完成し、最初のオーナーを含めた3人のイタリア人オーナーを経て1971年7月に日本に渡り、日本における最初のオーナーが所有していた時点でカー・グラフィック誌1972年1月号へ登場、その後の3人めとなったオーナーの時代に何らかの理由で眠りにつくことになった、とクルマの辿ったストーリーもハッキリしている。素性がすべてわかっている、ということだ。 デイトナ画像はこちら
デイトナ画像はこちら
ここまで条件が揃えば高額落札も当然、と考えるのはヒストリックカー好きだけの感覚なのかも知れないが、世の中の当たり前とは異なった限られた分野での当たり前というのが存在するのも事実。
ひと頃と較べればヒストリックカーたちの相場の高騰ぶりは落ち着きつつあるようなところもあるけれど、こうしたお宝の登場が、いつの時代も好き者にとっての美味い酒のアテになることに変わりはない。 デイトナ画像はこちら
デイトナ画像はこちら
この貴重なデイトナが今後どんなふうに仕上げられていくのか、僕達のような好き者はワクワクしながらその結末を知ることのできる日を待っているのである。