トラックメーカーまで一挙にご紹介
前回の「国産メーカー編その1」に引き続き国産メーカーのエンブレム、ブランドシンボルの由来を大調査! 普段何気なく目にしているシンボルマークも、その形に込められた意味を知るとこれから見る目が変わってくるかもしれない。
マツダ
「自らをたゆまず改革し続けることによって、力強く、留まることなく発展していく」というブランドシンボル制定のマツダの決意を、未来に向けて羽ばたくMAZDAの〈M〉の形に象徴しているのが、この「フライングM」と呼ばれるシンボルマーク。なお、「マツダ」という車名は創業者の松田重次郎氏の姓にちなんでいるほか、西アジアでの人類文明発祥とともに誕生した神、アフラ・マズダー(Ahura Mazda)にも由来している。
三菱
創業時の九十九商会が船旗号として採用した三角菱が現在のスリーダイヤ・マークの原型。これは岩崎家の家紋「三階菱」と土佐山内家の家紋「三ツ柏」に由来すると言われ、後に社名を三菱と定める機縁ともなった。スリーダイヤ・マークが商標登録されたのは1914年で、三菱グループすべてで使用されている。なお、同様のマークを使用する三菱鉛筆は三菱グループとは無縁の別企業である。
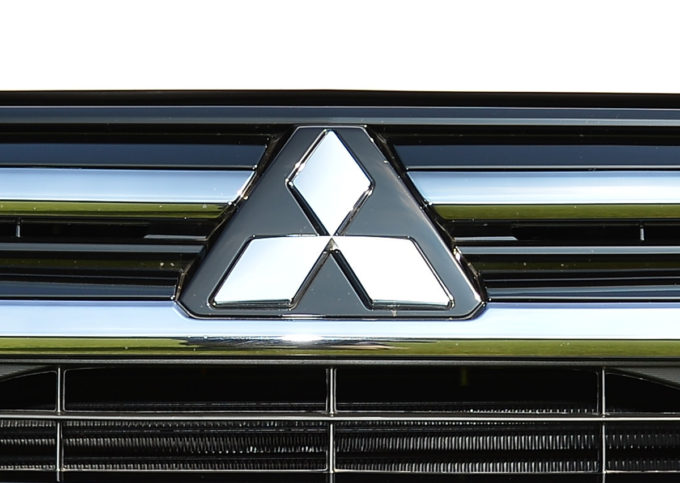
ダイハツ
ダイハツのエンブレムは「DAIHATSU」の頭文字「D」をかたどったもの。ダイハツはもともと「発動機製造株式会社」としてスタートしており、「大阪」の「大」と「発動機」の「発」をとってダイハツと略したことから始まっている。ちなみにエンブレムの「D」を囲う円は車種によってサイズが異なっているが、これはトヨタへOEM供給する際にトヨタマークと台座を共有するための苦肉の策である。
スズキ
スズキのエンブレムもダイハツ同様「SUZUKI」の頭文字である「S」をかたどったものであり、このエンブレムは1958年に作られたもの。発展するスズキのイメージをあらわすものとして、製品や印刷物や看板などにスズキのシンボルとして現在も使用されているのはご存知の通りだ。
いすゞ
「世界中のお客様に、心から満足していただける商品とサービスを創造し、社会に貢献するとともに、人間性豊かな企業として発展する」という当社の企業理念をシンボリックに表現したもので、ISUZUの文字をシンプルでモダンなデザインによりマーク化したもの。ちなみに平成3年まで使用されていたISUZUマークは「お客様とともに伸びゆくISUZU」「社会との調和のもとに伸びゆくISUZU」の2つの柱を象徴したものだった。
日野
HINOの「H」を象徴し、未来に向けて挑戦し続ける日野自動車の活力と発展性を表現したもので、地平線から昇る太陽、日の出というイメージを持っている。
左右に引き合う形はHINOのハイテクノロジーと環境の調和を、左右に広がろうとする強い力は未来の飛躍を、そして矢印は安全な行き帰りというトラック・バスメーカー積年の願いともなっており、中央のラインは輸送道路、左右の曲線は幹線と末端をつなぐ「流通」の一体感などをも願って表現されたもの。

